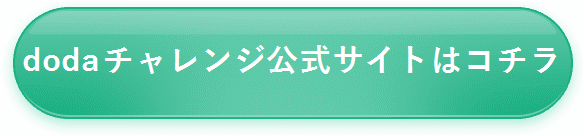dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や断られる人の特徴について解説します


なぜdodaチャレンジで求人紹介を断られることがあるのでしょうか?
転職活動を進める中で、dodaチャレンジに登録したものの「ご紹介できる求人がありません」と連絡を受けたり、エージェントからサポートを断られてしまうと、驚きや落胆を感じるかもしれません。しかし、そのような対応には明確な理由があります。その理由を理解し、適切な対策を講じることで、転職活動をよりスムーズに進めることが可能です。この記事では、dodaチャレンジで断られる主な理由と、その対処法について詳しく解説していきます。

断られる理由を理解し、対策を練ることが転職成功への第一歩ですね。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジでは、希望条件と企業の求人内容が一致しないと、「紹介可能な求人がない」と判断されるケースがあります。これは決してネガティブな評価ではなく、条件が厳しいために選択肢が狭まってしまっている状況とも言えます。特に以下のような希望を持っている方は、該当する求人が少なくなる傾向にあるため、結果として紹介されにくくなることがあります。

希望条件が多いと逆に紹介が難しくなることがあるんですね。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
在宅勤務や高収入といった条件を設定している場合、該当する求人は一気に減少します。特に障がい者雇用では、企業側も環境整備やサポート体制を考慮するため、柔軟な働き方を提供している職場は限られています。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
クリエイティブ系やアート系の職種は、障がい者雇用ではまだまだ数が少なく、一般職と比べると非常に限定的です。特定の業界に強くこだわってしまうと、紹介される求人が見つかりにくくなってしまいます。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方ではそもそも障がい者枠の求人が少ない傾向にあり、勤務地を限定してしまうと、dodaチャレンジが紹介できる求人の選択肢も限られます。勤務地の幅を広げることが選択肢を広げる鍵となります。

条件に柔軟性を持たせるだけで、一気にチャンスが広がりますね!
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジでは、求職者の状況や資格などに応じてサポートが行われます。そのため、一定の基準に達していないと判断された場合は、残念ながらサポート対象外とされる可能性があります。以下はその代表的なパターンです。

サポート対象にならないって、具体的にはどんな場合なんでしょうか?
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジは障がい者雇用を前提としたサービスのため、障がい者手帳が必要不可欠です。取得していない場合は、まず手帳の取得を検討する必要があります。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
ブランクが長く、職務経験が浅いと、企業側にとって即戦力として見られにくくなり、紹介の対象から外れる場合があります。まずは職業訓練やスキルアップを図ることで、選択肢を増やすことが可能です。
体調が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
体調面で安定していないと判断されると、dodaチャレンジとしては無理に転職をすすめず、まずは支援サービスを利用することを勧めるケースがあります。就労移行支援を活用して、段階的な社会復帰を目指すのも良い選択肢です。

サポート対象になるには、まず基本条件を整えることが大切ですね。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
面談は単なる手続きではなく、あなたの人柄や希望、適性を伝える大切な場です。しかし、しっかりと準備をせずに臨んでしまうと、エージェント側が適切な求人を紹介するのが難しくなってしまいます。以下のような準備不足や説明の曖昧さは、断られる一因になる可能性があります。

面談ってやっぱり第一印象や自己理解が大切なんですね。
障がい内容や配慮事項が説明できない
自分の障がいや必要な配慮を明確に伝えることができないと、dodaチャレンジ側も適切な職場環境を提案することができません。普段の生活や過去の職場経験などから、どのようなサポートが必要か整理しておきましょう。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「どこでもいい」といった姿勢では、自分に合った求人を見つけるのが難しくなります。自分の適性や希望職種について、ある程度の方向性や興味のある分野を持っておくことがスムーズな転職につながります。
職務経歴がうまく伝わらない
過去の仕事について、わかりやすく・簡潔に説明できないと、エージェントがスキルを正しく評価できません。職務経歴書を見直したり、話す練習をしておくと安心です。

面談前の準備が、求人紹介の可能性を大きく左右するんですね!
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
地方やリモート勤務を希望する人にとっては、求人の選択肢が狭まってしまうことがあります。dodaチャレンジは全国対応ではありますが、地域によっては求人自体が非常に少ないことも。そのため、地域性や通勤可否の柔軟さが紹介の可能性を左右することがあります。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
大都市圏に比べ、地方では求人の絶対数が少ないため、勤務地にこだわるほど紹介が難しくなる傾向があります。通勤の範囲を広げる、引越しも視野に入れるなど、選択肢を増やす工夫が必要です。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
完全在宅勤務は人気もあり、競争率が高いため求人は限られます。特に地方ではその傾向が顕著です。多少の通勤許容があると大きなプラスになることがあります。

勤務地や働き方に柔軟性があると、紹介の可能性が一気に上がるんですね。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
登録時の情報は、エージェントが求人を紹介するための判断材料となります。そのため、誤りや虚偽があると、トラブルを招いたり、紹介を断られる原因になります。以下のような事例には特に注意が必要です。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
実際には手帳を取得していないのに、登録フォームに「取得済み」と入力してしまうと、求人紹介の段階でトラブルになる恐れがあります。必ず正確な情報を記載しましょう。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
体調や環境面で働くのが難しい状況で登録してしまうと、ミスマッチが生じやすくなり、紹介されない可能性が高くなります。まずは就労可能な状態を整えることが先決です。
職歴や経歴に偽りがある場合
誤った情報を記載すると、面接や企業とのやり取りで信頼を失うことになります。dodaチャレンジは信頼性を重視しており、正確な情報の記載が何よりも重要です。

ちょっとした記載ミスや誤解も、紹介の機会を逃す原因になるんですね。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
紹介を受けたあと、企業の選考で不採用になると、「dodaチャレンジで断られた」と勘違いするケースがあります。実際には企業側の判断によるものであり、dodaチャレンジ側が求人を止めたわけではないことも少なくありません。
不採用は企業の選考基準によるもの
企業ごとに求める人材像は異なるため、書類選考や面接の結果として不採用になることもあります。一つの不採用にこだわらず、複数の求人に挑戦することが、転職活動ではとても大切です。

企業選考の結果はdodaチャレンジの責任じゃないって、意外と見落としがちですね。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか口コミや体験談を調査しました

実際に断られた人たちは、どんな状況だったのでしょうか?
ここでは、dodaチャレンジで求人紹介を断られたという声や体験談をまとめました。体験者たちの声からは、条件面や体調、スキルなど様々な要因が関係していることがわかります。自分のケースと照らし合わせて参考にしてみましょう。
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。
dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。
dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました

体験談を通して、dodaチャレンジが「断る理由」にはしっかりとした根拠があることがわかりますね。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について詳しく紹介します

dodaチャレンジで断られた後、どうすればいいの?他にできることってあるの?
dodaチャレンジから「紹介できる求人がありません」と言われてしまったとき、気持ちが沈んでしまうのも無理はありません。しかし、それで転職をあきらめる必要はありません。断られた背景を正しく理解し、次に向けた行動をとることが何よりも重要です。
スキルが足りなかったり、ブランクが長かったりと、様々な要因があるかもしれませんが、それらを補う方法はあります。改善ポイントを見つけて行動に移せば、チャンスは広がります。ここでは、断られた理由別に、どんな対処法があるのかを丁寧に解説していきます。

「断られた=終わり」ではなく、次のステップへのヒントが隠されているんですね!
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
「職歴が少ない」「特別なスキルがない」といった理由でdodaチャレンジから求人紹介を断られるケースは珍しくありません。ですが、そこで諦めるのはまだ早いです。自分の強みを見つけたり、スキルを積み重ねることでチャンスは広がります。ここでは、スキル・職歴面の課題を乗り越えるための具体的な対処法をご紹介します。

スキルや経験が少ないときって、どうやって自分を磨けばいいの?
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
ハローワークが提供している職業訓練は、スキル習得の第一歩として非常に有効です。Word・Excelなどの基本的なPCスキルから、データ入力といった事務に役立つ内容まで学べる講座が多数用意されています。ほとんどの講座が無料または非常に安価で受講できるため、経済的負担も少なく、再就職の準備として活用する人が増えています。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
就労移行支援は、障がいのある方が一般就労に向けた準備をするための制度です。ここでは、パソコンスキルや面接練習、職場体験などを通して実践的な力を身につけることができます。また、メンタルサポートや日常の相談ができる環境も整っているため、安心してステップアップを目指せます。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
「資格は自信の証」とも言われるように、取得することでスキルを客観的にアピールできるようになります。MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級は、特に事務職希望者におすすめ。求人票に「MOS資格保持者歓迎」と書かれていることも多く、紹介される可能性がグッと上がります。

無料や安価でスキルアップできる制度があるって、すごく心強いですね!
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養期間があるなど)の対処法について
「働きたい気持ちはあるけれど、ブランクが長くて不安…」そんな悩みを抱えている方も多いはずです。dodaチャレンジでは、長期間の離職や療養が理由で、サポート対象外となることもありますが、働く準備を少しずつ進めていくことで、再び求人を紹介してもらえるチャンスが生まれます。

ブランクがあるとやっぱり不利?でもできることから始めたいな。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
就労移行支援に通うことで、規則正しい生活リズムと就労の準備が身につきます。毎日の通所により体力や集中力も徐々に回復し、模擬業務や企業実習を通じて、リアルな職場経験を積むことも可能です。これらの経験は、再登録時の信頼材料にもなります。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
無理のない範囲から始めるのが大切です。週1〜2日のアルバイトや、体に負担の少ない在宅ワークなど、まずは「働ける自分」を取り戻すことを目的にしてみましょう。「短時間でも継続勤務ができた」という実績は、再チャレンジのときに強いアピールポイントになります。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
「働けるかどうか自信がない…」という方には、企業実習やトライアル雇用制度がおすすめです。実際の職場で短期間働く経験は、自己理解を深めたり、適性を見つける機会にもなります。また、こうした経験はdodaチャレンジ再登録時の有効なアピール材料になります。

小さな一歩を積み重ねれば、再チャレンジへの道も自然と見えてきますね!
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方に住んでいると、都市部に比べて障がい者雇用枠の求人自体が少なく、dodaチャレンジでの紹介が難しくなることがあります。特にフルリモート勤務を希望する場合、対応可能な企業も限られるため、選択肢がさらに狭くなるのが現状です。そんなときは、視野を広げて、複数の手段を組み合わせていくのがポイントです。

地方だとやっぱり選択肢が少ない…。でも在宅勤務ってどうにかならないのかな?
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
dodaチャレンジ以外にも、障がい者向けの転職エージェントは複数存在します。在宅勤務に特化した「atGP在宅ワーク」や、支援の手厚い「サーナ」「ミラトレ」などを併用することで、在宅勤務希望でもマッチする求人を見つけやすくなります。複数のエージェントに登録して、比較検討するのがおすすめです。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
今すぐ働き始めたい場合は、クラウドソーシングサイトで在宅の仕事を探すのも有効です。「ランサーズ」「クラウドワークス」などでは、ライティングやデータ入力など、スキル不要で始められる案件も多く、初心者でも取り組みやすいです。ここで作った実績は、将来的に在宅勤務の社員求人を目指す際にも役立ちます。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地方の求人は、地元の機関を頼ったほうが見つかりやすいケースがあります。ハローワークや障がい者就労支援センターでは、地元企業の求人情報を保有していることが多く、まだネットには出ていない求人と出会える可能性もあります。特に「人手不足の地域」では、地元の採用意欲が高まっていることもあります。

地方だからといってあきらめず、いろんな方法を組み合わせることで道は開けますね!
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
「完全在宅で、週3日勤務、しかも年収は高めが希望…」など、希望条件が多すぎると、dodaチャレンジでマッチする求人が見つからない可能性が高まります。すべての条件を満たす求人は非常に希少なため、柔軟に条件を見直すことが転職成功の鍵になります。ここでは、条件が厳しいと言われたときの対処法をご紹介します。

理想の条件を全部叶えたいけど…全部はムリってこともあるのかな?
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
全ての希望を叶えようとすると、紹介できる求人が極端に限られてしまいます。そこで大切なのが条件に優先順位をつけること。例えば、「完全在宅が絶対」という方も、週1回の出社を許容すれば対象求人が一気に広がることもあります。「譲れない条件」と「理想だけど妥協できる条件」を整理しておくと、より現実的な選択がしやすくなります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
一度断られたとしても、希望条件を見直してアドバイザーに再提示することで、状況が好転することがあります。たとえば、「週5勤務が難しいなら週4日勤務に」「フルリモート希望だが、月1出社なら可能」など、現実的に譲歩できるラインを見直すことで、紹介対象となる求人が見つかる可能性が広がります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
最初から理想の条件にこだわるのではなく、現実的な条件で一度就職して、キャリアアップしながら最終的に理想の働き方を目指すという考え方も重要です。たとえば、まずは時短勤務で経験を積み、体調や仕事に慣れたあとでフルタイムに移行する、専門性を高めて在宅専門職にステップアップするなど、計画的な道のりを設計することで、着実に理想に近づけます。

理想にこだわりすぎず、一歩ずつ段階を踏むことで希望の働き方に近づけるんですね!
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジは障がい者雇用枠に特化したサービスであるため、障がい者手帳の有無が紹介可否の判断材料となります。精神障がいや発達障がいの方の中には、手帳の取得で悩んでいるケースも多く、支援区分の違いなどで登録できなかったという声もあります。しかし、まだ可能性をあきらめる必要はありません。ここでは、手帳未取得や障がい区分で断られた場合の対処法を解説します。

手帳がないと登録できないって聞いたけど、それってどうしたらいいの?
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
精神障がいや発達障がいであっても、一定の基準を満たせば手帳を取得できます。まずは主治医に診断書作成の相談をし、居住地の市役所や区役所にある福祉窓口で手帳取得の条件や手続きについて確認してみましょう。取得できれば、障がい者雇用枠での求人紹介が可能になり、選択肢が一気に広がります。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳がない場合でも、ハローワークや就労移行支援事業所では「手帳なしOK」の求人が見つかることがあります。まずはそこで就職実績を作り、その後に手帳取得→dodaチャレンジ再登録という流れで、より条件の良い求人にステップアップする方法もおすすめです。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
就職活動を焦るよりも、まずは体調を整えることが最優先という場合もあります。主治医と相談しながら、治療と向き合い、体調が安定してから手帳を申請し、dodaチャレンジに再登録することで、よりマッチした求人に出会えるチャンスが広がります。

今は難しくても、準備を進めていけば再挑戦のチャンスはきっとあるんですね!
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
もしdodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかったとしても、他にも頼れるサービスはたくさんあります。自分に合ったサービスを見つけることで、道は開けます。
たとえば、障がい者向け転職エージェントには「atGP」「サーナ」「ラルゴ高田馬場」などがあります。それぞれ在宅勤務や職業訓練に特化していたり、メンタルサポートが充実しているなど、異なる強みを持っています。また、地元密着型の求人を探すなら、地域の障がい者就労支援センターやハローワークを活用するのも非常に有効です。
転職活動はひとつの道にこだわるのではなく、複数の選択肢を試すことが成功の秘訣です。焦らず、少しずつ自分に合った働き方を探していきましょう。

dodaチャレンジで断られても、道は他にもある。柔軟に考えて行動すれば、必ず次のステップが見えてきます!
dodaチャレンジで断られた!?精神障害や発達障害だと紹介は難しいのかについて解説します

精神障害や発達障害があると、dodaチャレンジでの求人紹介ってやっぱり難しいの?
dodaチャレンジを利用してみたけれど、「ご紹介できる求人がありません」と言われた経験のある方もいるかもしれません。とくに精神障害や発達障害を持つ方にとっては、「もしかして自分の障がいのせいで無理なのかも…」と不安になってしまうこともありますよね。
ですが、実際には障がいの種類だけで判断されているわけではありません。紹介が難しくなるのは、障がいの特性だけでなく、希望条件や就労経験など複数の要因が関係していることが多いです。ここでは、身体障害と比べた精神・発達障害の就職の傾向、dodaチャレンジでの対応などをわかりやすく解説していきます。

障がいの種類だけが問題じゃない。条件の見直しや準備次第で未来は変えられるんですね。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障害者手帳を持つ方の就職状況は、精神障害や発達障害の方とは少し異なります。企業側としても配慮すべき点が明確であるため、比較的スムーズに受け入れられやすい傾向があります。ただし、障害の部位や程度、業務との適性によって、求人の選択肢が広がったり狭まったりすることがあります。

身体障害があると、他の障害と比べて就職しやすいって本当?
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障害者手帳で軽度(例:6級・5級など)の等級を持つ方は、一般のオフィスワークや軽作業など、応募可能な職種の幅が広くなる傾向があります。企業側も大きな配慮を必要としない場合が多いため、比較的前向きに受け入れてもらいやすいのが特徴です。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
障害の内容が視覚的・明確に伝わることで、企業は事前に適切な配慮を準備しやすくなります。たとえば車椅子の方にはバリアフリー対応、手が不自由な方には特別な入力機器など、事前に対策がとりやすいことが、採用の後押しになります。
企業側が合理的配慮が明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
身体障がいに対する合理的配慮は具体的で明確なことが多いため、企業としても準備しやすく、安心して採用に踏み切れるケースが多いです。オフィスの設備改修や、業務内容の一部調整など、対応が比較的シンプルなことが理由です。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
一方で、通勤や作業に制限がある障がい部位の場合は、求人が限られる傾向があります。階段しかない建物や手作業の多い業務には適応が難しいことも。ただし、在宅勤務可能な仕事や身体的負担の少ない職種を選ぶことで、働きやすい環境は見つかります。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、対人スキルやコミュニケーションに問題がなければ、営業や受付など一般職種への採用も十分可能です。実際、障がいよりも「円滑なやり取りができるかどうか」を重視する企業も多く、採用の幅が広がります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がい者の多くが応募しやすいのがPC業務や事務職です。身体的な負担が少なく、在宅勤務の可能性もあるため、長期的に働きやすい環境が整っているケースが多いです。基本的なPCスキルがあれば、選べる求人の数も大幅に増えます。

身体障がい者の方は、職場での配慮も具体化しやすく、企業にとっても採用しやすいケースが多いんですね。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障害を持つ方が就職活動をする際、企業が特に気にするのは「安定して勤務できるかどうか」です。過去に長期間の休職や離職を繰り返していた場合は、企業側も慎重になりがちです。そのため、生活リズムを整え、安定して働ける状態にしておくことが非常に重要です。定期的な通院や服薬管理などを続けることも信頼につながります。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障害や発達障害は外見からは分かりにくいため、企業側は「どのような配慮が必要か」「突然休職したりしないか」といった不安を抱くことが多いです。そのため、応募時や面接時に「自分はどのような環境で安定して働けるか」を明確に伝えることで、不安を軽減し、採用の可能性が高まります。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
面接の場では、自分の障がい特性や必要な配慮について具体的かつ簡潔に伝えることがポイントです。たとえば、「電話対応が苦手」「業務指示は書面でほしい」「月1回の通院が必要」など、企業が対応しやすい内容に整理して伝えると好印象につながります。逆に、配慮事項が多すぎると企業が対応困難と判断することもあるため、可能であれば「最小限の配慮で働けること」も伝えておくと良いでしょう。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
知的障害のある方が取得する療育手帳は、その等級(判定区分)によって就職の選択肢が大きく異なります。A判定(重度)とB判定(中軽度)で支援の内容や就職可能な職種が異なるため、自身の状態をよく理解して、適切なステップを選ぶことが大切です。

療育手帳って、A判定とB判定でどれくらい違いがあるの?
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳には重度(A判定)と中軽度(B判定)があり、A判定の方は福祉的就労(就労継続支援B型)を選ぶ方が多く、B判定の方は一般就労の道も開けやすいという違いがあります。自分に合った働き方を選ぶためには、まず判定区分とその支援内容を正しく理解することが必要です。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定の方は、一般企業での就労が難しいケースが多いため、「就労継続支援B型」などの福祉的就労を活用することが多くなります。B型事業所では、自分のペースで作業スキルを身につけることができるため、無理なく働くための準備段階として有効です。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定の場合は、軽作業や事務補助、清掃業務など、比較的負担の少ない職種での一般就労が可能となるケースが多いです。また、支援機関や職場でのサポートが整っていれば、通常枠での雇用も現実的に目指すことができます。

判定区分や支援制度をうまく使えば、知的障がいの方にもいろんな就職チャンスがあるんですね!
障害の種類と就職難易度について
障がい者雇用枠の求人においては、障がいの種類や程度によって就職のしやすさが異なるのが実情です。一般的には、企業が配慮しやすく、障がいの特性が理解されやすいケースほど、採用のハードルは低くなる傾向があります。

障がいの種類によって、やっぱり就職の難しさって違うんですね…
たとえば、身体障がい(軽度〜中度)は就職しやすい傾向があり、必要な配慮が明確なため、企業側も対応しやすくなっています。反対に、精神障害や発達障害は「見えにくい障がい」であり、企業側の理解や対応が求められるため、ややハードルが高くなることもあります。
また、知的障害(療育手帳)の場合は、B判定(中軽度)の方は就職の可能性が比較的高い一方で、A判定(重度)の方は福祉的就労が中心になることが多いです。
それぞれの障がいに応じた適切な準備と対策を行うことで、就職のチャンスは確実に広がります。dodaチャレンジで断られたとしても、他の支援サービスや福祉機関を上手に活用しながら、自分に合った働き方を見つけることが大切です。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |

自分の障がい特性を正しく理解して、それに合った働き方を探すことが、転職成功の第一歩ですね!
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
障がいのある方が就職活動をする際には、「障害者雇用枠」と「一般雇用枠」のどちらで応募するかを選ぶ必要があります。それぞれの枠には異なる特徴があるため、自分の状態や希望する働き方に合わせて選択することが大切です。理解しておくだけで、転職活動の進め方が大きく変わる可能性もあります。

障害者枠と一般枠って、何がどう違うんだろう?どっちを選べばいいの?
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は、法律に基づき企業に義務づけられている雇用制度です。企業は障がい者が働きやすいように、就労環境を整える必要があり、面接段階から配慮について話し合えるのが特徴です。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
2024年4月からは障害者法定雇用率が2.5%に引き上げられ、企業はより積極的に障がい者を雇用する義務を負うようになります。これにより、障害者枠での求人は今後さらに増えていくと考えられます。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者枠では、障がいの種類や配慮が必要な内容をあらかじめ企業に伝えた上で採用されるのが一般的です。そのため、通院や作業ペースなどの要望についても企業側と話し合いながら進めることができます。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠では、障がいの有無にかかわらず、スキルや経験を基準にした選考が行われます。そのため、障がいによる配慮は基本的に考慮されず、他の応募者と同じ条件で評価されることになります。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般枠では、自分の障がいを企業に開示する(オープン)か、開示しない(クローズ)かを選ぶことができます。開示することで配慮が受けられるケースもありますが、クローズの場合は配慮を期待せずに働く覚悟が必要です。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、特別な配慮を求めることは難しいのが現実です。通院や作業環境への配慮を希望する場合は、障害者枠の方が適しているケースが多いでしょう。無理なく働くためには、自分の障がい特性に合った職場選びが重要です。

無理せず働くためにも、自分に合った枠を選ぶのが大事ですね!
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障がい者の就職活動においては、年齢によって採用の難易度が変わる傾向があります。若年層の方が比較的有利とされる一方で、年齢が上がるほど採用のハードルが高まるという現実もあります。ここでは、年代別の就職傾向や対策について詳しく解説します。

年齢によって、やっぱり就職のしやすさって違うの?私は40代だけど不利なのかな…
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
厚生労働省の「障害者雇用状況報告(2023年)」によると、障害者の法定雇用率は2.3%で増加傾向にあり、2024年4月以降は2.5%に引き上げられる予定です。これにより、今後さらに雇用機会が広がると期待されています。
とはいえ、年齢別で見ると、20代〜30代の若年層は未経験OKの求人も多く、比較的採用されやすい傾向があります。一方で、40代以降になると即戦力が求められる求人が増えるため、経験やスキルがない場合には難易度が上がるという課題があります。
また、障害者雇用枠での主な職種(事務職、軽作業、清掃など)は、体力や柔軟性が求められることもあり、若年層のほうが優遇されやすい面も否定できません。
とはいえ、年齢を重ねていても、スキルや実績をアピールできれば十分に採用の可能性はあります。特に、PCスキルや専門分野での経験がある場合、在宅勤務や専門職求人などで活躍できるチャンスも増えています。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
|---|---|---|
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |

年齢が高くても、スキルや経験を活かせばチャンスはしっかりあるってことですね!
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
「年齢が高いと、就職エージェントを使えないのでは…?」と不安になる方もいるかもしれません。実際、dodaチャレンジをはじめとした障がい者向け転職エージェントには公式な年齢制限は設けられていませんが、ターゲット層には一定の傾向があります。ここでは、年齢とエージェント利用について詳しく解説します。

年齢が高くなると、エージェントって使えなくなるのかな?ちょっと心配…
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
公式には年齢制限は設けられていませんが、実質的に50代前半くらいまでがメインターゲットとなっている傾向があります。企業側は「できるだけ長く働いてもらいたい」と考えるため、若年層〜中高年層(20代〜50代前半)の求人が多いのが現実です。
ただし、50代後半や60代であっても、豊富な経験や専門スキルが活かせる求人や、短時間勤務・在宅勤務などの柔軟な働き方が可能な求人は存在します。エージェントにこだわらず、他の支援機関も併用するのが賢い選択です。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
50代以上で就職活動に不安がある方は、ハローワークの障がい者窓口や、障がい者職業センターの利用も視野に入れましょう。これらの公的支援機関は、年齢に関係なく利用でき、職業訓練や職場体験、個別相談などの手厚いサポートが受けられます。
特に、障がい者職業センター(高齢・障害・求職者雇用支援機構)は、就職に向けた実践的なサポートや就労準備支援が充実しているため、ブランクがある方や未経験職への挑戦を希望する方にぴったりです。
dodaチャレンジなどの民間エージェントと、公的機関をうまく併用することで、年齢に関係なく、より多くの可能性を広げながら就職活動を進めることができます。

年齢が高くても、経験や柔軟な働き方を活かせば道はまだまだ開けますね!
dodaチャレンジの口コミはどう?についてよくある質問

dodaチャレンジの評判って実際どうなの?利用前に不安なことを確認しておきたいな…
dodaチャレンジを利用しようと考えている方の中には、「口コミや評判は実際どうなんだろう?」「万が一断られたらどう対処すればいいの?」といった不安や疑問を感じている方も少なくないはずです。
ここでは、そんな声に応える形で、dodaチャレンジに関するよくある質問をわかりやすくまとめました。実際の体験談を交えながら、利用前に知っておきたいリアルな情報をご紹介していきます。
さらに、詳しい内容を知りたい方のために、関連ページのリンクもご案内していますので、気になるテーマがあればあわせてチェックしてみてください。

事前に疑問を解消しておけば、不安なくdodaチャレンジを活用できますね!
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの利用者からは、「求人の紹介がスムーズだった」「カウンセリングが丁寧だった」といった良い口コミがある一方で、「希望する求人がなかった」「面談後に連絡が来なかった」といった意見もあります。
実際の口コミや評判について詳しく知りたい方は、以下の関連ページを参考にしてください。
関連ページ:dodaチャレンジの障害者雇用はおすすめ?口コミや特徴、メリット・デメリットを徹底検証!
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで「紹介できる求人がありません」と言われたり、登録を断られたりすることもあります。しかし、原因を理解し適切な対策をとることで、再びチャンスを得ることは可能です。
例えば、スキル不足が理由なら職業訓練を受けたり、他の障がい者向け転職エージェントを併用するのも方法の一つです。詳しい対処法は、以下の関連ページで解説しています。
関連ページ:dodaチャレンジは本当に難しい?断られた理由と対処法、体験談を徹底解説
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジの面談を受けた後、「連絡が来ない…」と不安に感じる方もいるかもしれません。
面談後に連絡がない理由として、求職者の希望条件とマッチする求人が見つからない、企業との調整に時間がかかっている、または連絡の行き違いなどが考えられます。
具体的なケースや対処法については、以下の関連ページで詳しく紹介しています。
関連ページ:dodaチャレンジからの連絡なしの原因は?面談・求人・内定の状況別に理由と対策を解説!
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、職務経験や希望条件、障がいの特性、必要な配慮などについて詳しくヒアリングされます。
事前に準備しておくと、スムーズに対応できるため、面談の流れや聞かれることを事前に確認しておくと安心です。
詳しくは、以下の関連ページで解説しています。
関連ページ:dodaチャレンジ面談完全対策:内定までの流れを把握し、注意点と入念な準備で成功を掴む!
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がい者の転職支援に特化したエージェントサービスです。
登録すると、専任のキャリアアドバイザーが付き、求職者の希望や適性に合った求人を紹介してくれるのが特徴です。企業とのマッチングや選考対策、面接の調整などのサポートも受けられるため、転職活動を効率的に進めることができます。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジの求人は、基本的に「障がい者雇用枠」が対象となるため、障がい者手帳を持っていない場合は紹介が難しくなることがあります。
ただし、手帳の取得を検討している場合は、アドバイザーに相談することで、手続きに関するアドバイスを受けられることもあります。
関連ページ:dodaチャレンジを手帳なしで使える?障害者手帳が必要な理由や申請中の対応を紹介
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジでは、障がいの種類に関係なく登録が可能ですが、支援の対象外となる場合があります。
例えば、長期間のブランクがあり職歴がほとんどない場合や、体調が不安定で継続勤務が難しい場合は、就労移行支援を勧められることもあります。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジを退会したい場合は、担当のキャリアアドバイザーに連絡するか、公式サイトの問い合わせフォームから手続きを行うことができます。
退会の際は、今後の転職活動に影響がないよう、事前に確認しておくと良いでしょう。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、オンライン(電話・Web面談)で実施されることが一般的です。
また、対面での相談を希望する場合は、拠点があるエリアでの面談が可能なこともあるため、事前に確認すると良いでしょう。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには公式な年齢制限はありませんが、実際には50代前半までがメインの対象となっています。
50代後半以降の求職者は、ハローワークの障がい者窓口や、障がい者職業センターを併用することで、より多くの求人情報を得ることができます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中でもdodaチャレンジに登録し、転職活動を進めることができます。
ただし、直近の職歴がない場合やブランクが長い場合は、紹介される求人が限られることがあります。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは基本的に「転職エージェント」のため、新卒向けの求人は少なく、学生の利用は難しい場合があります。
就職活動を進める際は、大学のキャリアセンターや新卒向けの障がい者就職支援サービスを併用すると良いでしょう。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスと比較

dodaチャレンジって断られることもあるの?他のサービスと何が違うのか気になるな…
dodaチャレンジを利用しようと考えている方の中には、「本当に求人を紹介してもらえるの?」「他の障がい者向け就職サービスと何が違うの?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。
実際、dodaチャレンジでは、求職者の状況や希望条件によっては、求人を紹介されなかったり、登録を断られたりすることもあります。ですが、それはdodaチャレンジに限った話ではなく、他の障がい者就職支援サービスでも同様のケースは珍しくありません。
重要なのは、各サービスごとの特徴を把握し、自分に合ったサポートを受けることです。どのサービスが自分に向いているのかを見極めることで、転職成功の可能性は大きく広がります。
ここでは、dodaチャレンジの特徴を押さえつつ、他の代表的な障がい者向け転職サービスとの違いについても比較しながら、わかりやすく解説していきます。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
|---|---|---|---|
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー (atGP) |
1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビ パートナーズ紹介 |
350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援 ミラトレ |
非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッド チャレンジ |
260 | 東京、神奈川、 千葉、埼玉、大阪 |
全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、 東海、福岡 |
全ての障害 |

サービスの違いを知ることで、自分に合ったサポートを受けられる可能性がぐっと高まりますね!
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談まとめ

結局、dodaチャレンジで断られる理由ってどんなことが多いの?どうやって対処すればいいの?
dodaチャレンジは、障がい者のための転職支援サービスとして多くの実績がありますが、誰にでも必ず求人を紹介してくれるわけではありません。希望条件が厳しすぎたり、職歴が浅い、体調が安定していない、障がい者手帳が未取得など、さまざまな要因により紹介が難しくなるケースもあります。実際、体験談にもあるように、「在宅希望だった」「ブランクが長かった」「専門職を希望しすぎた」といった理由で断られた方も少なくありません。
ただし、それらは「今の条件ではマッチする求人がない」というだけのことで、今後の行動次第でいくらでも状況を変えることが可能です。スキルアップのために職業訓練や就労移行支援を活用したり、条件を少し柔軟に見直すことで、新たな可能性が広がります。また、公式FAQでも解説されているように、他の障がい者向け転職サービスとの併用や、ハローワーク、障がい者職業センターなどの公的支援機関を利用することで、より多くの選択肢を得ることもできます。
大切なのは「断られた=終わり」ではなく、「次にどう動くか」です。dodaチャレンジで断られても、それは自分に合う他の道を見つけるきっかけになるかもしれません。今回の記事では、dodaチャレンジの断られやすいケースとその対処法を網羅的に紹介していますので、自分の状況と照らし合わせながら参考にしてみてください。

「断られた経験」は、むしろ自分の可能性を広げるチャンスになります。前向きに進んでいきましょう!